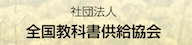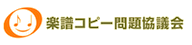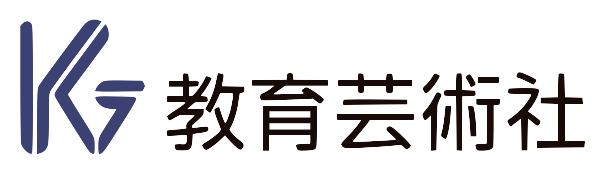| 東京都: |江戸の鳶木遣|葛西囃子|神田囃子|
|
江戸の鳶木遣 |
|
木遣は,全国で歌われています。祭礼で 声を長く 「江戸の鳶木遣」は,東京都の |
| トップへ |
葛西囃子 |
|
東京都葛飾区にある葛西神社のお祭りで演奏されるお囃子が「葛西囃子」です。今から300年ほど前に,神主であった能勢 環によって始められました。その後,周辺地域に広く伝わったため祭り囃子の元祖ともいわれています。 長胴太鼓,締太鼓,鉦,篠笛の楽器が用いられますが,楽譜はなく,楽器のリズムや音の感じを言葉で表した唱歌を何回も歌い覚えて演奏します。 曲は「屋台」「昇殿」「鎌倉」などがあり,一定の順序で続けて演奏されます。他にもお面を着けておどる曲や獅子舞の曲などがあります。 現在は,保存会を中心に伝統を守りながら受けつがれ,地域の小学校などでは子どもたちも演奏しています。 |
| トップへ |
|
神田囃子
|
| 神田囃子は,千代田区外神田にある神田神社(神田明神)で行われる神田祭で演奏されます。 神田囃子の由来としては,建久3年(1192年),源 頼朝公が征夷大将軍に任ぜられ,鶴岡の神社前で盛大な祭りが行われたときに,五人囃子を奉納したのが始まりとする説や,葛西囃子と関係があるとする説などがあります。 楽器の編成は,大太鼓1人,締太鼓2人,篠笛1人,鉦1人の5人(五人囃子)です。篠笛は「トンビ」ともいわれ,なだらかな美しい音色を出します。また,鉦は「よすけ」といって,ほかの4人を助ける大事な役割を担います。 この5人の座る位置は決まっていて,正面から向かって,前列の左から大太鼓・締太鼓の真・締太鼓の流の3人が座り,後列は左から鉦・篠笛の順で座ります。  撮影場所:神田明神 神楽殿 神田囃子は,「地囃子」といって,打込,屋台,昇殿,鎌倉,仕丁目,屋台の6曲が基本となり,順に演奏されます。初めの締太鼓の独奏が「打込」です。続く「屋台」は,悪魔払いの曲だといわれ,篠笛に始まり締太鼓が入ります。そして,鉦・大太鼓という順で「昇殿」が続きます。これは「聖天」と書かれることもありますが,地囃子を代表する曲です。歌舞伎でも,祭礼の場面や元気のよい人物が登場するときに用います。「鎌倉」は神前で奏でる静かな曲です。「仕丁目(四丁目)」はゆるやかな曲調です。最後の「屋台」は,初めと同じ曲にもどります。 このほかにも,「獅子」「投げ合い」など数曲の囃子があります。 神田祭について,少しふれてみましょう。江戸時代,江戸市中を回り歩く祭り「江戸大祭」の一つとされ,また,将軍に見ていただくため神輿が江戸城に入ることを許されたことから,「天下祭」といわれていました。神田囃子は神田祭につきものとして,上は将軍,下は庶民まで広く楽しまれていたそうです。 同じく江戸の祭りとして,日枝神社の山王祭があります。こちらも神田祭と同じく,盛大に行われていましたが,年々,たがいの盛大さを競うようになっていったそうです。そのため,天和元年(1681年)以来は町民の負担を軽くするように,1年おきに交代で祭を行うようになりました。つまり神田祭は,本祭りの年に盛大に祭礼を行い,陰祭りの年には,山王祭のほうが盛大な祭礼を行うようになったのです。 そのころの神田祭は,旧暦の9月15日に行われていましたが,明治以降の現在は,5月中旬(年によってちがいますが,10日ごろから15日まで)に行われています。 今でも,本祭りの年の神田祭は,神社の御霊を入れた山車が練り歩いたり,各町からたくさんの神輿が出たりするなど,規模が大きな祭が行われます。その際,神田囃子は屋台の上で演奏されるほか,神田明神の神楽殿でも演奏されるのです。 【参考曲】 葛西囃子 江戸里神楽 |
| トップへ |