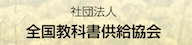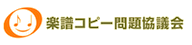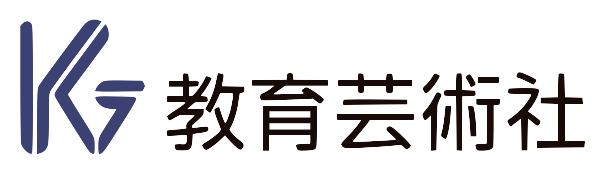尺八
尺八は竹でできた縦笛の仲間です。長さが全体でおよそ1尺8寸あるところからこの名前になりました。「尺」とは昔使われていた長さの単位で,1尺は約30.3cmになります。
指穴は表側に4つ,裏側に1つあり,これだけの穴で2オクターブ半の音域の音をすべて表現することができます。
こと(箏)と同じように尺八もまた,もともと日本に存在していた楽器ではありません。「古代尺八」というものが最も古く,唐の時代の中国で生まれ,奈良時代になって日本に伝わったとされています。この古代尺八は当時,雅楽の合奏曲に用いられていましたが,平安時代中期になって絶えてしまいました。今では,正倉院や法隆寺に数本が残されているだけです。
室町時代には,再び中国から「一節切」と呼ばれる尺八が伝わってきました。この尺八がもとになって,元禄年間に「普化尺八」という日本独特の楽器が生まれました。
江戸時代には,戦乱や政策によって生じた多くの浪人たちが虚無僧となって普化宗を組織していました。虚無僧は,テレビの時代劇などで見かけるように,編み笠を深くかぶって,お経を唱えるかわりにこの普化尺八を演奏して歩きました。江戸時代中期の虚無僧であった黒沢琴古(1710〜1771)は,多くの新作を発表して1つの流派を開きましたが,これが現在でも広く普及している琴古流の起源となりました。
明治4(1871)年に普化宗が廃止されると,尺八は宗教用の楽器ではなく,1つの楽器としてあつかわれるようになり(江戸時代には,一般の人々が尺八を演奏することは禁じられていました),やがて,箏や三味線と合奏されるようになりました。
現在,一般に尺八として広く使われているのは,この普化尺八です。
【参考曲】
・「春の海」