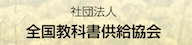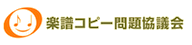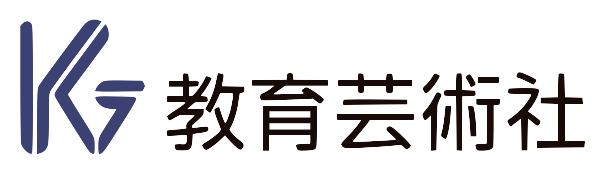こんぴら船々 |
香川県を代表する民謡である「こんぴら船々」の歌詞は,以下のようなものです。
金毘羅船々 追手に帆かけて
シュラ シュ シュ シュ
廻れば四国は 讃州那珂の郡
象頭山 金毘羅大権現
(一度廻れば)
あまり聞いたことのない言葉も出てきますので,内容について説明してみましょう。
「金毘羅大権現」は,古くから航海や海にかかわる神さま,「こんぴらさん」として親しまれていました。瀬戸内海は,昔から漁業や船での運送業が盛んだったこともあって,船で旅する人が安全に航海できるようにお願いしたり,漁師たちが豊漁になるようにお願いしたりするため,「こんぴらさん」をよくお参りしたそうです。
その金毘羅大権現があったのが,「讃州の那珂の郡」にある「象頭山」という山の中腹です。讃州とは,讃岐のことで,香川県の昔の呼び名です。また,那珂の郡とは,金毘羅大権現(今の金刀比羅宮)がある地域の昔の呼び名です。象頭山は,香川県西部にある琴平山の別の呼び名になります。
さて,江戸時代になると,「こんぴらさん」は全国的に有名になっていて,願い事をかなえてもらおうと大阪や九州などからも,たくさんの人々がお参りに来たそうです。そうしたお客さんを乗せて,大阪などの港と香川県北西部にある丸亀港との間を往復した船のことを,金毘羅船と呼びました。
「追手」は「追風」と書くこともあり,追い風(順風)を帆に受けて,金毘羅船が進む様子が目にうかびます。「シュラ シュ シュ シュ」は,波の上をおだやかに船が進んでいく様子を歌っているといわれています。
以上,簡単に説明しましたが,「こんぴら船々」の歌の様子をイメージすることができたでしょうか。
金刀比羅宮は石段の多さでも有名で,参道の登り口から御本宮までは785段,さらに奥社まで行くと,1368段にもなり,現在,年間およそ350万人の人たちが訪れています。 |
 |
| トップへ |
|
讃岐獅子舞 |
讃岐獅子舞は,香川県内に数多く伝えられている獅子舞を,まとめて呼ぶときの名前です。
讃岐国は,香川県の昔の呼び方で,獅子舞とは,「獅子頭」と呼ばれるかぶりものをかぶって演じる踊りや舞のことです。
昔の人は,獅子を空想上の生き物としてとらえていて,聖なる力をもつその獅子が舞うことで,悪魔や病気を追いはらい,幸せなことを呼びこむことができると考えていました。
県内の神社の周りには,いくつもの集落があり,秋祭りには集落ごとに獅子舞を神社に奉納していたそうです。そのため,いろいろな舞が生まれ,また,獅子頭や油単と呼ばれる獅子の胴体に当たる部分の布の絵柄もさまざまなものになりました。使用される楽器には,たらいのような大きさの鉦や,太鼓などがあり,獅子の舞に合わせて演奏されます。
現在,県内には獅子組と呼ばれる団体が800くらいあるといわれています。
毎年,秋になると,各地の神社の祭礼で演じられていましたが,今では各地の獅子舞を集めた「獅子舞王国さぬき」などのイベントも開かれており,地元に住んでいない場合でも獅子舞にふれることができる機会が多くなっています。
数ある獅子舞の中でも,家浦二頭獅子舞,虎頭の舞,尺経獅子舞,吉津夫婦獅子舞,綾南の親子獅子舞の5つは,香川県の無形民俗文化財として指定されています。 |
 |
| トップへ |
|
JASRAC許諾 M1303283012,9016192015Y45038
〒171-0051 東京都豊島区長崎1丁目12番14号 Phone:03-3957-1175 / Fax:03-3957-1174
Copyright 株式会社教育芸術社 All Rights Reserved.