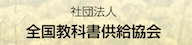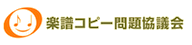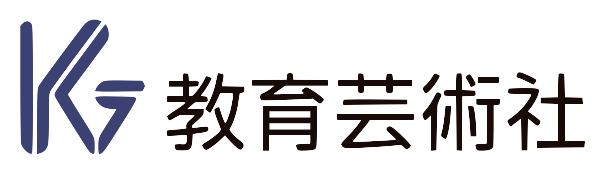| 滋賀県: | 大津祭囃子| 江州音頭|
|
大津祭囃子 |
大津祭は,琵琶湖の南西岸にある大津市で行われる祭りです。江戸時代の始めに天孫神社の古木に住んでいたたぬきが死んでしまい,その古木をなぐさめるために踊ったのが始まりといわれています。 現在,10月上旬に行われるこの祭りでは,13基の曳山が町を練り歩きます。祇園祭の曳山をまねてつくったという大津祭の曳山は,三輪で,二重構造になっています。それぞれの曳山には,「からくり人形」がのせられていて,本祭りの巡行中,およそ20ヶ所でからくりが演じられます。これは「所望」と呼ばれ,曳山ごとにいろいろなテーマで演じられます。 大津祭のお囃子は10種類ほどあり,曳山によって名前がちがいます。どの曳山にも共通するお囃子としては,「宵山」や「戻り山」があります。「所望」のお囃子もそれぞれの曳山にありますが,曲はそれぞれ異なっています。 お囃子は,鉦,太鼓,笛で構成されていて,曳山に乗った囃子方といわれる人たちによって,演奏されます。 お囃子用の楽譜はなく,笛や太鼓はきいて覚えるのですが,鉦には音を直接書き取った覚え書きがありますので,一部を紹介します。 【鉦の覚え書きの例】 「よいやま」 かんかんかんかん かんちきちっち かんかんちきち かんちきちっちん かんちきちきちきちん ちきちっち たたき方には,「かん」「ちん」「ち」「ちき」があります。「かん」は,鉦の真ん中をたたきます。「ちん」は,左側から左下にかけてのあたりをたたいて,止めずにはらいます。「ち」は左側をたたき,はらわずに戻ります。「ちき」は,左下,右上の順に連続してたたきます。 地域の人たちは,子どものころから祭りの前になると公民館などに集まってお囃子の練習を行います。町のあちこちから鉦や笛の音が聞こえ,祭りのムードを盛り上げます。 県内には,ほかにもお囃子があります。水口囃子と日野囃子は,江戸の「神田囃子」の流れをくむもので,大津祭など祇園祭系のお囃子の多い西日本ではたいへんめずしいものです。 |
| トップへ |
江州音頭 |
「江州音頭」の源をたどると,奈良時代や平安時代にさかのぼります。「声明」と呼ばれる仏教のお経のふしが元になっていると考えられています。 江戸時代の終わりごろ,八日市の西沢寅吉は,当時流行していた踊りなどを取り入れて村々で音頭を歌い,人気者になりました。明治時代の始めに,豊郷の千樹寺観音堂が再建されたときには,西沢の音頭にのって,村人たちが踊り明かしたといわれています。 やがて,この音頭は豊郷・八日市を中心に近江路一帯に広がり,「江州音頭」として定着しました。 歌詞の中には,お米などの穀物が豊かに実ることを神仏にいのりをこめて願う部分,そして,人々の心の内にある喜怒哀楽を表現する部分があります。大地に生活し,実りを願い,そして一人一人の心のうったえを語り合う庶民の歴史がこの中にはあります。 現在,江州音頭は夏の盆踊りに県内各地で歌い踊られています。 踊り場の中央に櫓を組み,音頭取りがその上で金杖をならし,あるいは法螺貝を吹いたりします。ときどき口で「アー,れれれん,れれれん,れれれん」といい,太鼓,三味線などを伴奏に歌います。この「れれれん」は法螺貝の擬音です。地域の人たちは,この歌に合わせて櫓の周りを踊ります。 今も,多くの人たちによって歌い踊られ,地域の人たちの大切な交流の場にもなっているのです。 |
| トップへ |
三重県側の 「鈴鹿馬子歌」は,この厳しい鈴鹿峠を行き来し,馬に荷物や人を乗せて運んでいた馬子とよばれる人たちが歌ったものがもとになったといわれています。 鉄道の 〽坂は 鈴鹿は あいの 歌詞にある「坂」は鈴鹿峠の三重県側にあった坂下宿,「土山」は滋賀県側にあった土山宿のことです。坂下宿では太陽が照っているのに,鈴鹿峠では曇ってきて,峠を越えたあとの土山宿では雨が降っている,というように,鈴鹿峠を境にして天気が変わりやすかった様子がうたわれています。 土山宿がある滋賀県 ※坂下宿や土山宿の「宿」は,「しゅく」と読んだり言ったりすることがあります。 |
| トップへ |