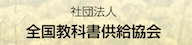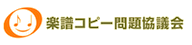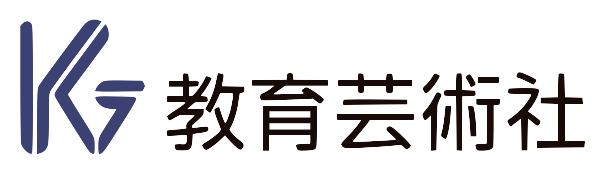|
網のし歌
|
「網のし歌」は,「磯節」と同じく茨城県を代表する民謡の一つです。
昔から平磯や那珂湊,大洗のあたりは漁業が盛んに行われていました。漁をするためには,ねらう魚の種類や大きさによって,網の目の大きさがちがうものを使っていて,平磯の辺りでは,まぐろ漁をするときに,特に目の粗い大目網を使っていたそうです。
この大目網は編まれたままでは網の結び目が締まらないので,浜などの開けたところに網を広げて20~30人の人が引き合って結び目を固く締めていました。この作業を「目のし」といい,「網のし歌」はこの作業を行いながら歌われたといわれています。
昭和30年ごろに,尺八演奏家の谷井法童さんによって,現在の形に整えられ,三味線や尺八などの伴奏が加わって歌われるようになりました。
歌詞の一部を紹介します。
〽のせや のせのせ 大目の目のし
のせば のすほど アレサ目が締まる
〽わたしゃ湊の 荒浜育ち
波も荒いが アレサ気も荒い
「ヨイノセ」や「コラショ」などのはやし言葉も加わります。
|
 |
| トップへ |
|
|
磯節
|
「磯節」には,新しいものを含めると数多くの歌詞がありますが,もともとは那珂川河口近くの大洗や那珂湊の辺りで,漁師たちが古くから歌っていた歌が元になっているようです。
いつごろから歌い始められたかははっきりしませんが,明治時代の初めごろになって,俳人でもあった渡辺竹楽坊が歌詞や囃子言葉を補足したといわれています。ほかに,藪木萬吉やその娘たちが三味線の伴奏などを加えて歌ったともいわれています。
このように,だんだんと洗練されてきた磯節ですが,水戸や大洗などの限られたところでしか,歌われていませんでした。
その磯節が全国に広まった理由の一つに,水戸出身の横綱である常陸山と,美声の持ち主であった関根安中との出会いが挙げられます。水戸に帰ったあるときに,常陸山は関根安中の歌った磯節をきいて,たいそう気に入りました。そこで,常陸山は安中を相撲の巡業に連れて行き,行く先々で磯節を歌わせたそうです。テレビのなかった時代ですが,いろいろな場所で歌われて,磯節の名はしだいに広まっていきました。やがて,「安中の磯節か,磯節の安中か」とまで評判になり,安中の独特の歌い回しから「安中節」とも呼ばれました。
現在では,県内の各市町村の文化芸術祭や地域のお祭りなどで歌われています。また毎年2月には磯節全国大会も開かれ,全国から多くの参加者を集めています。
|
 |
| トップへ |
|
JASRAC許諾 M1303283012,9016192015Y45038
〒171-0051 東京都豊島区長崎1丁目12番14号 Phone:03-3957-1175 / Fax:03-3957-1174
Copyright 株式会社教育芸術社 All Rights Reserved.