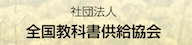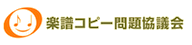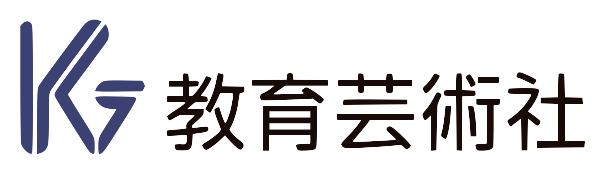| 福島県
|
会津磐梯山 |
| 「会津磐梯山」は,福島県会津地方の盆踊り歌として,会津に伝わる民謡の中でも,最も親しまれている歌です。磐梯山のふもと,猪苗代町で「民謡会津磐梯山全国大会」が開かれていることからも分かるように,会津だけでなく,全国的にも親しみをもって歌われています。お盆には,たくさんの人が故郷へ帰ります。その人々が集い,櫓を組み,「会津磐梯山」をお囃子に,仮装をしたり踊りを楽しんだりしています。 福島県民謡全集によると,「会津磐梯山」は,一般には明治初年ころに越後の五ヶ浜(今の新潟県西蒲原郡)のあたりから来た職人さんが,今の会津若松市を訪れたときに歌い踊った「五ヶ浜甚句」が元になっているといわれています。当時,この歌は単に「盆踊り歌」と呼ばれ,その踊りは「かんしょ踊り」といわれていました。「かんしょ」とは,会津地方の方言で「熱狂的になる様子」のことです。この歌に合わせて,老いも若きも自由な服装で思い思いに振りを付け,とびはねながら踊ったそうです。 会津若松市では,8月の上旬に「流しかんしょ踊り」が開かれ,現在もその形が残っています。 その後,会津に広まったこの歌は,各地で工夫が加えられ,やがて現在のような歌詞や踊り方の民謡「会津磐梯山」の形になりました。「小原庄助さん なんで身上つぶした…」という囃子言葉の軽やかさとともに,今では福島県を代表する盆踊り歌となっています。 【注】
|
| トップへ |