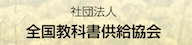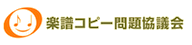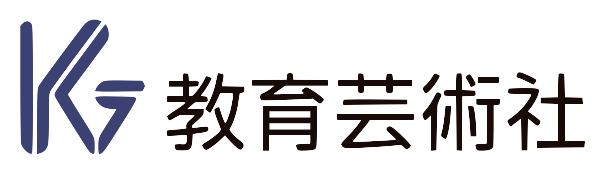| 沖縄県: |
|
|
この歌は, 「安里屋ユンタ」の 「ユンタ」は, また,昭和9(1934)年に
|
| トップへ |
|
エイサー
|
| エイサーは,沖縄県を代表する踊りで,昔から沖縄本島を中心に行われている芸能です。エイサーが行われるのは,お盆(旧盆)の期間中が主ですが,学校行事のメインである運動会では一番の盛り上がりを見せてくれます。それは,小学校ばかりではなく,保育園,幼稚園をはじめ,中学校,高等学校,大学の学園祭まで会場をわかせてくれます。 沖縄県でエイサーが最も盛んなところは中頭(中部)ですが,国頭(北部)や,島尻(南部)でも行われており,学校・地域が一つになって取り組める芸能・踊りです。 エイサーは,歌・三線(三味線)に合わせて若い男女がいっしょに踊るのが普通ですが,地域によっては男のみで踊るところ(嘉手納町・千原)があれば,女のみのところ(大宜味村・喜如嘉)もあります。エイサーは,もともと村の各家庭を一軒一軒訪ねて夜通し踊り,お盆の夜を楽しんだものですが,今では,村の道々や広場で早い時間から始まり,夜の11時ころ(ウークイの時間)には終わる習慣に変わってきています。 エイサーの由来は,祖先に豊作を感謝し,来年の豊作を祈願するという説,村内の悪い者をパーランクーなどの音で払い清める目的というところもあり様々ですが,お盆にあの世からやって来たご先祖様たちにごちそうをふるまって,供養するという信仰が芸能化したともいわれています。現在では新築祝いや結婚披露宴など,お祝い事で踊ることもあります。 エイサーを踊るときは,パーランクーという太鼓や締太鼓,そして赤太鼓(大太鼓)を使い,伴奏に歌・三線で盛り上げ,素手で舞う男女がいるのが一般的です。また,服装も鮮やかなものが多い中,白と黒で質素なものもあります。いずれにしても旧盆の夜に行われるエイサーも,灼熱の太陽,炎天下で踊る祭り的なエイサーも,熱く燃えるものがあり見ている人を引き付け,興奮させてくれます。 大きなイベントとして,沖縄全島エイサーまつりがあり,全島各地から青年団が集まり,華やかな演技がくり広げられます。2003年で48回目を数えたこのエイサーまつりでは,色とりどりの衣装で勇壮に舞い,観光客の目を楽しませてくれます。 エイサー保存会としては,勝連町(中頭)の平敷屋エイサーが世界に誇れる民族芸能として2003年には結成20周年の記念祝賀会を行いました。そのほかにも,名護市(国頭)の世冨慶エイサー保存会などがあり,沖縄の伝統芸能は各地で受けつがれています。 県外においても神奈川県や兵庫県,大阪府などでも盛んになってきているようです。2003年6月には東大駒場祭で東京大学沖縄県人会の1・2年生がエイサーを初披露したことも新聞で報道されております。このようにして,エイサーは沖縄にとどまらず,国内はもちろんのこと外国(ブラジルやボリビアなど)でも多くの人々に愛されるようになり,世界のエイサーになりつつあります。 【注】三線…沖縄の三味線のこと。 ウークイ…ご先祖様をお送りする(15日)こと。 (ウンケー…ご先祖様をお迎えする(13日)こと。 沖縄のお盆は,旧暦の7月15日(13日〜15日)。) |
| トップへ |
谷茶前 |
沖縄には約六千という数多くの曲がありますが,大きく二つに分けることができます。一つは古典音楽,もう一つは民謡です。古典音楽は,曲想が重厚で厳粛な儀式歌の役割をもっており,琉球王朝時代に中国からの使者を歓待するためのうたげで演じられました。一方,民謡は,庶民の心が生み出したもので,生活感覚,風俗,伝説,古謡などと深い関係をもち,時代の流れにのって今なお新しい民謡が作り出されています。「谷茶前」は,この民謡に属しています。 那覇から約40kmの西海岸沿いに続く沖縄一細長い村である恩納村は,近年大型リゾートホテルが海岸線にできて,たくさんの観光客を集めています。その恩納村の真ん中あたりに谷茶というところがあり,国道58号線の西の丘に民謡「谷茶前」の碑が建っています。 昔の谷茶は海と山にはさまれた土地で耕地は少なかったのですが,養豚や漁業が盛んでした。ところが100年ほど前に大火に見まわれ大きな打撃を受けて以来,半農半漁のさびしいところとなっていました。 「谷茶前」は,谷茶の前の浜の漁村風景をスケッチふうにえがいた民謡で,男と女のちがった振り付けで踊ります。男はカイを持ち,短い芭蕉布の仕事着に前結びの白はちまきで,女はザルを持って琉球絣に紺のしごき帯をきりっと前にしめ,たがいにもつれて軽快に踊ります。テンポの速い甘いリズムの歌曲と,健康的で生活感あふれる舞踊です(現在は女二人で踊られ,一方が男役を踊ります)。 琉球王府の尚敬王が国頭巡視の際(1726年)に,万座毛で休憩したときに芸能を出して歓待したといわれ,そのとき,谷茶の人たちは「谷茶前」を演じたといわれます。 谷茶前の歌詞と訳
1 谷茶前ぬ浜に スルル小が 寄てぃてぃんどーへー スルル小が 寄てぃてぃんどーへー ナンチャ マシマシ スルル小が 寄てぃてぃんどーへー ディアングァヤクシク 【訳】 谷茶村の前の浜に ああ なるほどざわめいている キビナゴが寄り集まっているよ さあ 娘さんそれはよいことだ 急いで 約束の時間だよ 2 スルル小やあらん 大和ミジュンどぅ やんてぃんどーへー 大和ミジュンどぅ やんてぃんどーへー ナンチャ マシマシ ディアングァヤクシク 【訳】 キビナゴではないよ 大和いわし なんだってよ 3 アッピー達やうり取いが アン小や かみてぃうりういがーへー アン小や かみてぃうりういがーへー ナンチャ マシマシ ディアングァヤクシク 【訳】 お兄さんたちは それを取りに 娘さんたちは 魚を頭上に乗せて それを売りに 4 うり売てぃ戻いぬ アン小が 匂いぬ しゅらさーへー アン小が 匂いぬ しゅらさーへ ナンチャ マシマシ ディアングァヤクシク 【訳】 魚を売って帰りの 娘さんの 香りの 香ばしいことよ 娘さんの 香りの 香ばしいことよ ※これらとは異なる歌詞もあります。 |
| トップへ |
月ぬ |
|
「月ぬ美しゃ」は, 〽月ぬ 日本には古くから,十五夜の満月は美しいとしてお月見をする習わしがあります。 3年生で歌った「うさぎ」という歌にも,〝十五夜 お月さま〟という歌詞がありましたね。 十三夜の月は,満月より少し欠けてはいますが,十五夜の満月に次いで美しいといわれています。 満月になる前の十三夜の月の美しさと,大人になる前の自分とを重ねて歌っていたのかもしれません。 また,別の歌詞にも月の美しさにふれられるものがあります。 〽 東の空に満月が上がってくる夜。 お月さまに向かって「沖縄も八重山も照らしてください」と この「月ぬ美しゃ」の歌詞の終わりには「ホーイ チョーガ」という,はやし言葉が入るため,「チョーガ節」といわれることもあります。 ※八重山地方の方言の発音には特有のものがあるため,歌詞の表記は一つの例として示しています。
|
| トップへ |