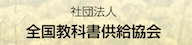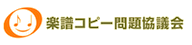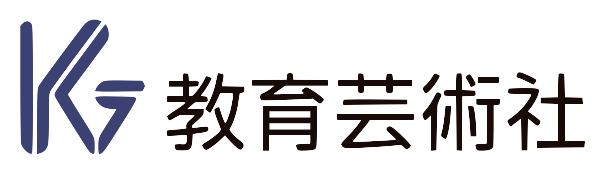| 三重県: |石取祭囃子|伊勢音頭| 桑名の殿さん|
|
| 「桑名石取祭」は,8月の第一土,日曜日に,桑名市にある春日神社を中心に行われる行事です。「石取祭」は,神社に奉納するために町屋川(員弁川)で石を拾い集める「石取り」と呼ばれる行事がもとになったとされています。 石を新しい俵に入れ,小さな車に乗せて鉦や太鼓を打ち鳴らしながら,夜になると,ちょうちんをつけて神社に奉納したそうです。 この小さな車が,今に伝わる祭車の始まりです。現在は,より大きく美しくなっており,40数台の祭車が祭りをいろどります。 祭車の後部には,長胴太鼓が1つ置かれ,4~6個の大きな鉦がつるされています。 石取囃子は,これらの楽器をリズムに合わせて打ち鳴らします。リズムや打ち方は各町や地域によってちがいますが,ビンロージと呼ぶ木製のトンカチ状のものを使用して鉦を打つため,とても大きな音で演奏されるお囃子としても有名です。 平成28(2016)年,「桑名石取祭の祭車行事」として,ユネスコ無形文化遺産の代表一覧表に記載されました。 |
| トップへ |
| 三重県にある伊勢神宮は,参拝のために全国から船や徒歩で多くの人が集まったため,昔からたいへんにぎわっていました。その人たちが,伊勢に宿泊したときに歌い覚えたものを,自分たちの故郷に戻ってからも歌ったために,「伊勢音頭」と呼ばれる歌は,いろいろなかたちで全国に広まっていったといいます。 また,伊勢音頭の起源についてもいろいろな説がありますが,その中の一つとして,伊勢神宮の建物をつくるための木材を運ぶ仕事(「御木曳」)をするときに歌われた木遣り歌がもとになっているというものがあります。木遣り歌とは,御木曳のときなどに音頭を取りながら歌う仕事歌の一つです。伊勢の木遣り歌には「ヤートコセ」という囃しことばがあり,その言葉が伊勢音頭の中にも含まれていることがその理由です。 現在伝わっている歌にしても,その起源にしても,「伊勢音頭」にまつわるものは多々ありますが,三重県を代表する民謡であることに違いはありません。 |
| トップへ |
桑名の殿さん |
| 「桑名の殿さん」という民謡は,「クワナのトノさん,シグレでチャちゃづけ」と唄います。桑名のお殿さまのようにぜいたくをしている人が,ハマグリの佃煮のお茶づけを食べてほっとする,という意味です。 昔の東海道は,名古屋から桑名まで海を30kmほどわたらなければなりませんでした。その間には,大きな3つの川がよりそうように流れていて,昭和の初めになるまで橋がなかったからです。少しでも波が高くなると船は出すことができなかったため,昔の桑名には,船を利用する人や荷物のためのお店がたくさんあって,とてもにぎわっていました。 また,桑名の近くの海の中は,たくさんのハマグリでとてもにぎわっていました。3本の川が,貝の住みやすい砂を運んで来てくれたからです。特に味のよくなる秋から冬のハマグリは,佃煮も作られていました。このハマグリの佃煮がとてもおいしいので,俳句で有名な松尾芭蕉の弟子が,佃煮を作る季節に合わせて「時雨」と名前をつけたそうです。 この桑名から東海道をはなれて三重県をずっと南へ行くと,昔から全国の人が一度はお参りを夢みた伊勢神宮があります。伊勢神宮へのお参りを終えた人々は,おみやげの一つとして「ヤートコセーヨーイヤナ,アリャリャ」という掛け声の入った唄を覚えてきました。この掛け声は,伊勢神宮を建てかえるときの木材を運ぶときに唄う「御木曳木遣り唄」から生まれたものです。この掛け声のある唄の中でも,「伊勢は津でもつ〜」という唄は「伊勢音頭」として全国に広がって,各地で「祝い唄」や「盆踊り唄」になりました。 「桑名の殿さん」にも,同じようなかけ声が入っていますので,もとは「御木曳木遣り唄」であったと考えられています。さらに全国のあちこちの海辺にある「○○の殿さん,○○で茶ちゃづけ」というかえ唄にも,ちゃんと同じ掛け声が入っています。 【参考曲】 道中伊勢音頭 鈴鹿馬子唄 |
| トップへ |
三重県側の 「鈴鹿馬子歌」は,この厳しい鈴鹿峠を行き来し,馬に荷物や人を乗せて運んでいた馬子とよばれる人たちが歌ったものがもとになったといわれています。 鉄道の 〽坂は 鈴鹿は あいの 歌詞にある「坂」は鈴鹿峠の三重県側にあった坂下宿,「土山」は滋賀県側にあった土山宿のことです。坂下宿では太陽が照っているのに,鈴鹿峠では曇ってきて,峠を越えたあとの土山宿では雨が降っている,というように,鈴鹿峠を境にして天気が変わりやすかった様子がうたわれています。 土山宿がある滋賀県 ※坂下宿や土山宿の「宿」は,「しゅく」と読んだり言ったりすることがあります。 |
| トップへ |