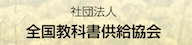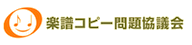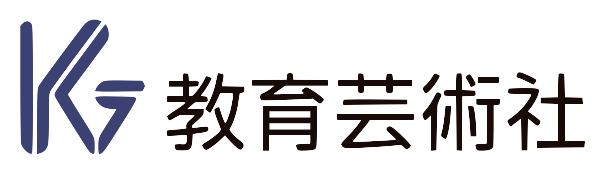| 福井県: | 越前紙漉き唄| 三国節|
|
越前紙漉き唄 |
| この民謡は,越前和紙の里として知られる福井県越前市(旧:今立郡今立町)の五箇と呼ばれる地域(大滝・岩本・不老・新在家・定友)で,紙漉きの仕事とともに歌いつがれてきた仕事歌です。 「越前紙漉き唄」は,紙漉きの歴史や昔からの仕事の様子などが分かりやすい歌詞で,「川上御前(紙漉きを伝えたといわれる神様)から授かった紙漉きの仕事が,親から子,子から孫へと受けつがれ,清い心と清い水,これからもいっそう辛抱(努力)して,よりよい紙漉きを続けていきたい。」と歌っています。 この民謡は,越前和紙の里に住む人びとが,紙を漉くときだけでなく,おたがいの親睦を深めあう集まりの時など,日ごろの仕事への感謝の気持ちをこめて歌われてきました。今でも男女,年齢を問わず日々の様々な場で歌う姿が見られます。「越前紙漉き唄」は永い紙漉きの歴史と共にはぐくまれてきたといえるでしょう。 |
| トップへ |
三国節 |
| 「三国節」は,現在の福井県三国地方に伝わる民謡の一つです。 この曲の由来には,江戸時代,三国にある神社の土地を地固めするときに歌った作業歌がもとになったという説と,船頭が船をこぐときなどに歌っていたものがもとになったという説があります。この辺りは九頭竜川の河口にあり,港町として栄えていたため,その歌がいろいろなところで歌われるようになり,だんだんと土地になじむように変化していったと考えられています。 明治時代になると,一時的にあまり歌われなくなりましたが,レコードによる民謡ブームのおかげで再び注目されるようになりました。現在では,北陸地方を代表する祭りの一つである三国祭や地元のお祭りなどで歌われています。 |
| トップへ |