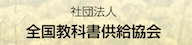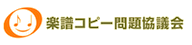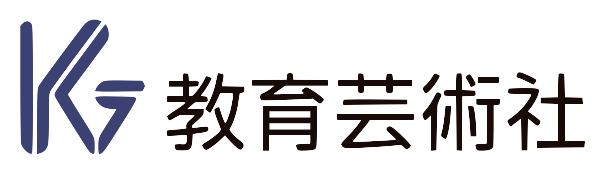| 岩手県: | さんさ踊り | 南部牛追い歌|
|
|
さんさ踊り
|
| 岩手県盛岡市にある三ツ石神社には巨大な石があります。その巨石にはさんさ踊りの由来があるといわれています。 昔,この地方に鬼が現れ,悪事をくり返したことがありました。困り果てた人々が三ツ石神社に鬼の退治をお願いしたところ,神様はその鬼をつかまえ,二度と悪事を働かないことをちかわせました。そのあかしとして,鬼は三ツ石神社の境内にある巨石に手形を残して退散しました。人々はたいへん喜び,「さんさ,さんさ」と言いながら石の周りを踊ったといいます。これがさんさ踊りの始まりになったというものです。 さんさ踊りは,南部藩の各地で伝えられてきましたが,現在のように統一されたふり付けで,通りをパレードするようになったのは昭和50年代に入ってからです。「南部」というのは昔の国の名前の一つで,今の盛岡地方がそれに当たります。 8月の初めに行われる「盛岡さんさ踊り」では,太鼓と笛の音が街中にひびきわたり,2万人もの踊り手によってエネルギッシュな踊りが披露されます。 |
| トップへ |
|
南部牛追い歌
|
| 南部牛追い歌は,岩手県を代表する民謡の一つで,およそ400年も前から歌われてきた美しい曲です。牛の背に荷物 をのせて遠くまで運ぶ人たちが,牛といっしょに歩きながら歌った歌です。 塩や木炭などを牛の背にのせて,海抜1,000メートルぐら いの峠を往復するためには,馬よ りも牛のほうが強かったようです。一人で7〜8頭の牛をグループにして,数十頭の牛でキャラバン(隊列)を組んで歩きました。時には,山の中で野宿をすることもありましたので,食料や炊事用具な ども持ち歩いたようです。 牛を連れて歩く人(牛方)たちが歌った歌(牛方節)が元になって,少しずつ改良されて現在歌 われている牛追い歌になりました。岩手県は,藩制時代に「南部藩」といわれていましたので「南部牛追い歌」といいます。 現在歌われている代表的な歌詞は, 田舎なれども南部の国は 西も東も金の山 です。 金がたくさんほり出されたころのことをほこらしげに歌っています。このほか にも,牛をいたわるような歌詞や,通過した土地の様子を歌った歌詞などがたくさんあります。 平野部では,馬に荷物をのせて運ぶ人(馬方)が歌う歌「南部馬方節」という民謡もあります。牛追い歌と同じように,ゆったりした 気持ちの歌で,ふしはちがっても歌の感じは牛追い歌に似ています。 岩手県では,9月末に南部牛追い歌(南部牛追唄)全国大会が行われています。 【参考曲】 南部牛方節 南部馬方節 岩崎鬼剣舞 |
| トップへ |